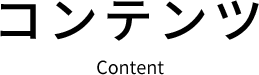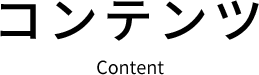釧路には旧石器時代から縄文時代、擦文時代(北海道の飛鳥時代~鎌倉時代)、アイヌ文化にわたる遺跡が数多くありますが、釧路湿原に面する台地の上に大規模な国指定史跡があることをご存じでしょうか?竪穴住居の跡が数多く残る歴史的に重要な遺跡、それが北斗遺跡です。

北斗遺跡は、釧路湿原西縁の釧路市湿原展望台の近くにあります。道道53号から砂利の脇道に入り、手前にあるのが史跡北斗遺跡展示館、さらにその先にあるのが「擦文の村」と呼ばれる竪穴住居群の複合遺跡です。
 トイレや駐車場を完備した史跡北斗遺跡展示館
トイレや駐車場を完備した史跡北斗遺跡展示館
1977年7月に遺跡の東側が国指定史跡となり、「ふるさと歴史の広場」として整備され、史跡北斗遺跡展示館が建てられました。館内では、北斗遺跡から出土した土器・石器・金属製品のほか、内部の構造がわかる復元住居や1/150の史跡住居跡のジオラマも展示されています。

出土された土器や道具から、北斗遺跡は縄文時代から擦文時代を中心に、旧石器時代にも人々が暮らしていたことがわかったそうです。シベリアとのつながり、織物や糸、おかゆ状のキビなど、昔の人の生活が垣間見られる貴重な展示品が並びます。
 湿地のスゲの葉が茶髪の怪物のようになる「やちぼうず」の群生
湿地のスゲの葉が茶髪の怪物のようになる「やちぼうず」の群生
竪穴住居群の遺跡へは、展示館から15分ほどの道のりを歩きます。春先などの道中で群生した「やちぼうず」が見られるのは、釧路湿原に面する遺跡ならではの風景です。
 復元された竪穴住居
復元された竪穴住居
約800年前の「擦文の村」と呼ばれる竪穴住居群の遺跡には、竪穴のくぼみに復元された住居が建ち並び、中に入れるものもあります。

木製の史跡展望台からの景色。多くの竪穴のくぼみ、復元住居が見られ、釧路湿原に面する一画であることがわかります。北斗遺跡には、縄文時代の円形の竪穴が102軒、擦文時代の四角形の竪穴が232軒ほど残っているそうです。旧石器時代から擦文時代まで、約1万年以上にわたって人々が暮らしていたと思うと感慨深いものがあります。
雄大な釧路湿原の自然と古代からの歴史ロマンを体感できる北斗遺跡に、ぜひ一度足を運んでみてください。